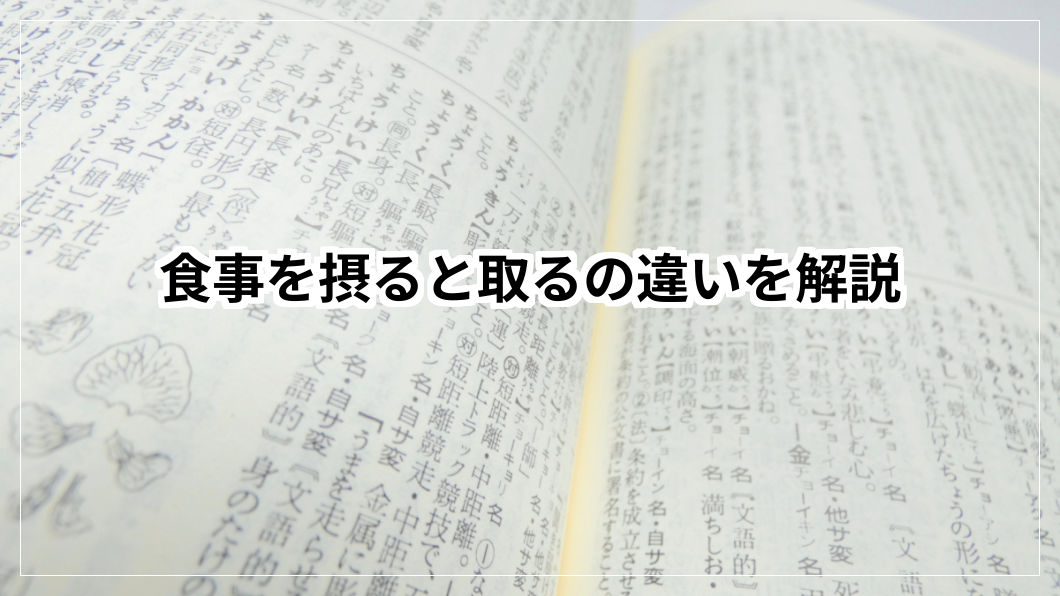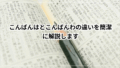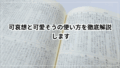食事に関する日本語表現には、「摂る」と「取る」という2つの漢字が用いられます。
一見似ているこの2語には、実は明確な意味の違いがあります。
本記事では、「摂る」と「取る」の違いを中心に、食事や栄養に関する日本語表現について詳しく解説します。
正しい言葉の使い分けを理解することで、文章の精度を高めましょう。
「摂る」と「取る」の違いとは
「摂る」の意味と使い方
「摂る」は「摂取する」の略として使われる表現で、主に栄養や水分などを身体に取り込むことを意味します。
例:ビタミンCを摂る、水分を摂る、栄養を摂る
「取る」の意味と使い方
「取る」は「手に入れる」「得る」という広い意味を持つ漢字で、予約を取る、時間を取る、休暇を取るなど多様な用途があります。
例:昼食を取る、資料を取る、成績を取る
言葉としての共通点と相違点
共通点は「何かを得る・得ようとする」点ですが、
「摂る」は主に健康や体内への取り込みに関係し、
「取る」はより幅広く抽象的な概念にも適用されます。
食事に関する言葉の使い方
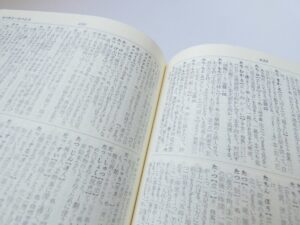
食事を摂るとはどういうことか
「食事を摂る」という表現は、単に空腹を満たす行為ではなく、身体に必要な栄養素やエネルギーを意図的かつ計画的に補給するという意味合いを含んでいます。
この表現は、医学や栄養学、健康指導など専門的な分野でよく使用され、食べるという行動が生理的・機能的な役割を果たすことに焦点を当てています。
特に、健康状態の維持や改善、成長の促進、病気からの回復といった目的をもつ食事において、「摂る」という言葉が適しています。
また、「食事を摂る」は、内容や栄養バランスを考慮した食事をとることを暗示しており、何をどのように食べるかという質的側面にも関心が向けられます。
例えば、病後の回復期には「しっかりと食事を摂る」ことが勧められ、これは単なる食事行為以上に栄養補給と体調管理の意味を強く持っています。
そのため、ビジネス文書や医療機関の案内など、正確で丁寧な言い回しが求められる場面で広く使用されています。
例:病後はしっかりと食事を摂りましょう。
食事を取ることの意味
日常会話における一般的な表現です。
例:昼休みに食事を取った。
日本語における食事の表現
丁寧な表現:「お食事を召し上がる」「食事をいただく」など。
くだけた表現:「ごはん食べる」「メシ行こう」など。
栄養の摂取と食事の関連性
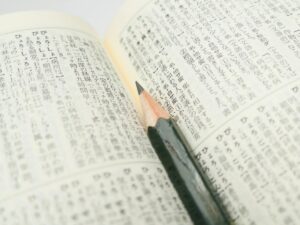
栄養を摂るための食事の重要性
「摂る」という言葉は、単なる「食べる」という行為を超えて、体内に栄養素を効率よく吸収するという意味を強く含んでいます。
そのため、健康維持や成長促進、病気予防といった観点から、どのような食事を摂るかが非常に重要になります。
特に、三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)だけでなく、ビタミンやミネラル、食物繊維といった微量栄養素の摂取も欠かせません。
現代人は偏った食生活や不規則な食事により、必要な栄養が不足しがちであり、そうした栄養バランスの乱れが生活習慣病や慢性疲労、集中力の低下などを引き起こす一因となっています。
このような背景から、「栄養を摂る」という行為は単に空腹を満たす以上の意味を持ち、体と心の健康を支える基礎としての役割を果たしているのです。
また、栄養の摂取は一回一回の食事だけでなく、日々の継続性とバランスのとれた積み重ねが重要であることも意識すべきです。
睡眠を摂ることとの関連
「摂る」は睡眠や休養にも使われることがあります。
例:十分な睡眠を摂ることで体調を整える。
栄養を取るための具体例
・バランスの良い食事を摂る
・ビタミンサプリを摂取する
「摂取」と「取り入れる」の明確な違い
摂取の辞書的な意味
「摂取」とは、栄養素や水分などを体内に取り込む行為を指し、主に医学的・生理的な文脈で使用される専門用語です。
この語は、食物や薬品を通じて人間の体が必要な成分を吸収するプロセスを表すため、健康や栄養、医療の分野では非常に重要な概念です。
また、摂取量やタイミング、吸収効率といった情報とセットで用いられることが多く、単に「食べる」「飲む」といった日常的な動作よりも、科学的な意味合いが強調されます。
例としては「ビタミンDの摂取量を調整する」「糖分の過剰摂取に注意する」などが挙げられます。
このように、「摂取」は量的・質的なコントロールが求められる文脈で使用されるのが一般的です。
取り入れるという表現の使い方
「取り入れる」という表現は、物理的なものだけでなく、概念的・抽象的なものを受け入れるという広い意味を持っています。
たとえば、部屋に風を取り入れる、日光を取り入れるといった物理的な例だけでなく、意見や価値観、新しい技術や考え方などを自分の中に取り込むといった文脈でも頻繁に使われます。
例:新しい考え方を取り入れる、最新の教育法を取り入れる、外国の文化を積極的に取り入れる。
このように、「取り入れる」は応用範囲が広く、抽象的・柔軟なニュアンスを持っているのが特徴です。
言葉の使い方にみる微妙なニュアンス
「摂取」=体内に取り込む(主に栄養・水分)
・使用場面:健康管理、医療、栄養指導など専門的な分野
・例:水分摂取、栄養摂取、カロリー摂取
「取り入れる」=物理的・精神的に受け入れる(文化、意見、習慣など)
・使用場面:日常会話、教育、ビジネス、社会的コンテキスト
・例:他国の文化を取り入れる、新しい制度を取り入れる、自然光を取り入れる
このように、両者は似ているようで用いる対象や文脈に違いがあり、言葉の選択によって伝わる印象や専門性に差が生まれます。
「食事を摂る」と「食事を取る」の用例
実際の使われ方リスト
・健康記事:「朝食をしっかり摂りましょう」
・日常会話:「昼ごはん取ってくる」
場面による使い分け
フォーマルな文脈:摂る
カジュアル・日常会話:取る
よく使われるフレーズ集
・栄養を摂る
・食事を取る
・睡眠を摂る
・休憩を取る
公用文における表記のルール
漢字の使い方と表記
「摂る」は医学的・専門的な文脈でよく使用される漢字であり、「摂取する」という語に由来しています。
そのため、やや堅い印象を与えることがあり、文脈によっては読みやすさや親しみやすさを優先して、平仮名の「とる」と表記されることもあります。
特に一般向けのパンフレットやWebサイト、案内文などでは、読者層を考慮して表記を柔軟に調整するケースが多く見られます。
また、教育現場などでも児童生徒が理解しやすいように、あえて平仮名で統一する例もあります。
公用文での適切な言葉の選び方
公用文や報告書、行政文書においては、意味が明確であること、かつ丁寧であることが求められるため、「食事を取る」よりも「食事をする」「昼食をとる」など、より中立で柔らかい表現が用いられる傾向にあります。
このような表現は、読み手に負担をかけず、同時に不要な専門性を回避する配慮として機能しています。
特定の行動を表現する際に、動作よりも目的や状況を重視することで、より円滑なコミュニケーションが図れるという利点もあります。
デジタル大辞泉における探究
『デジタル大辞泉』によれば、「摂る」は「摂取する」という語義に基づいており、特に栄養素や水分を体内に取り入れることを意味する際に使われるとされています。
この語は生理学的・医学的な文脈でしばしば登場し、「栄養を摂る」「水分を摂る」などの例文が典型的です。
一方、「取る」はより一般的・汎用的な語であり、同じ「食べる」行為を指すにしても、使われる文脈の幅が広いことが強調されています。
このように、辞書上でも語の専門性や使われ方におけるニュアンスの違いが明確に定義されています。
違いを理解するための練習問題
クイズ形式で学ぶ
Q:「水分を( )ようにしましょう。」
A:摂る
正しい使い方を確認する
Q:「昼ごはんを( )。」
A:取る
例文を作成してみる
・病気の回復には、栄養をしっかり摂ることが大切です。
・上司との昼食を取った。
日本語における新しい表現
食事に関する最近の使い方
SNSやチャットアプリなどを中心に、「めし摂取」「ランチ摂取中」などのユニークな言い回しが若者の間で使われ始めています。
これらの表現は、かしこまらずに食事を取っていることを伝える方法として広まり、日常の報告や気軽なコミュニケーションツールの一部となっています。
さらに、配信者やインフルエンサーが使用することで、一種のインターネットスラングとしての地位を確立しつつあります。
言葉の進化とその影響
「摂る」は元々、栄養を体内に取り入れるという医学的・科学的な意味で使われてきましたが、現代においてはやや堅苦しい印象を持たれることもあります。
一方で「取る」は汎用性が高く、SNSなどでも自然に使いやすい言葉として若年層に好まれています。
言葉の進化により、場面や対象者に合わせた柔軟な言い換えが重要視されるようになり、同じ意味を伝えるにも選択肢が増えている点が特徴的です。
若者言葉との関連性
「摂取タイム」「メシ摂ってくる」「栄養チャージ中」など、日常の食事や行動を擬人化・ネタ化して表現するスタイルが流行しています。
これらは単に食事を報告するだけでなく、自分の今の状態や気分を伝える手段にもなっており、仲間内での共感や笑いを生み出す一種の言語遊びとしても機能しています。
このような言葉の使い方からは、現代の若者文化やSNSコミュニケーションにおける言語の柔軟性がよく表れています。
食事と健康の関係性
健康的な食事を摂ることの重要性
栄養バランスを意識することは、健康を維持するうえで非常に重要です。
そのため、「摂る」という表現は、体内に必要な栄養素を取り入れるという目的を明確に示す言葉として適しています。
特に高齢者や成長期の子ども、妊娠中の女性など、特定の栄養素が求められる人々においては「摂取する」という行為自体が生活の質を左右する重要な要素となります。
また、栄養の過不足が引き起こす健康リスクについても、「摂る」という表現を使うことでより医学的な意味合いが伝わりやすくなります。
食事を取る方法の考察
一方で、「食事を取る」は行動面を指す言葉として非常に有効です。
例えば、「昼食を取る」「時間を取って夕食を楽しむ」といった表現は、食事を行動として捉え、生活のリズムの中に組み込まれていることを示します。
この表現は、ビジネスシーンや日常会話など、時間管理や人間関係と関わる場面で特に重宝されます。
誰と食べるか、どこで食べるか、どんな雰囲気で食べるかなど、食事の背景や環境を含めた広い意味での「行為」を指し示す際に「取る」が適しています。
栄養バランスを考えた食事とは
栄養バランスを考えた食事とは、単に量を食べるのではなく、質を重視して摂ることを意味します。
主食(ごはん・パンなど)・主菜(魚・肉・卵など)・副菜(野菜や海藻など)・汁物(味噌汁・スープなど)をバランスよく取り入れることが推奨されています。
さらに、カルシウムや鉄分、ビタミン類、食物繊維といった不足しがちな栄養素を意識して摂取することで、生活習慣病の予防や免疫力の向上にもつながります。
現代人にとっては外食や加工食品に頼りがちな生活習慣が栄養の偏りを引き起こしやすいため、日々の食事選びで「摂るべきもの」を意識する姿勢が求められます。
まとめ
「摂る」と「取る」は似て非なる言葉であり、文脈に応じた適切な使い分けが重要です。
栄養や健康を意識した表現には「摂る」、日常的・抽象的な行動には「取る」が用いられます。
正しい使い分けを身につけることで、表現力と文章の正確性が向上します。